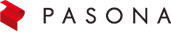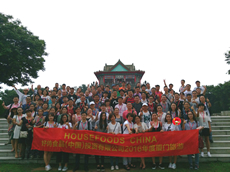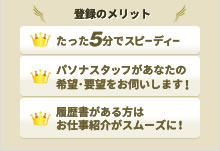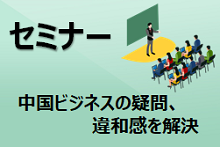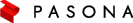2017年11月18日/第6回 JOB博CHINA@Tokyo 在中大手日系企業合同面接会のご案内
2017/08/31
Category : お知らせ,JOB博総合
050_中国でゴルフを楽しむ
2017/08/03
Category :
中国では経済的に豊かな人々の増加にともない、ゴルフ「高尔夫球(gāo’ěrfū qiú)」は中国でも人気のあるスポーツの一つになっています。ゴルフ場「高尔夫球场(gāo’ěrfū qiúchǎng)」にはたくさんの外国人が来場することから、フロント「前台(qiántái)」やキャディー「球童(qiútóng)」の中には、外国語ができるスタッフも多く、ゴルフを楽しむうえで、中国語は必ずしも必要ではありませんが、ゴルフ用語を知っていれば、キャディーや中国人プレーヤーとの会話も楽しめるので、中国での余暇の過ごし方の幅も広がるのではないでしょうか。
ウッド 木杆(mùgān)
アイアン 铁杆(tiěgān)
パター 推杆(tuīgān)
スイング 挥杆(huīgān)
ティーグラウンド 发球台(fāqiútái)
ホール 球洞(qiúdòng)
フェアウエー 球道(qiúdào)
ラフ 乱草区(luàncǎoqū)
バンカー 沙坑(shākēng)
グリーン 果岭(guǒlǐng)
A:球童,这个球道多少码?
Qiútóng, zhège qiúdào duōshao mǎ?
キャディーさん、このホールは何ヤードですか?
B:大概是四百二十码。二百二十码附近右边有沙坑,不要打右旋球。
Dàgài shì sì bǎi èr shí mǎ. Èr bǎi èr shí mǎ fùjìn yòubian yǒu shākēng, búyào dǎ yòuxuán qiú.
大体420ヤードです。220ヤードの辺りの右手にバンカーがあるので、スライスに気をつけて下さい。
A:谢谢。那给我一号木杆。
Xièxie. Nà gěi wǒ yí hào mùgān.
ありがとう。では、ドライバーを下さい。
以前は、駐在員がゴルフに行くときは、日本人だけで集まることが多かったのですが、最近ではビジネスの関係で中国人といっしょにラウンドする機会も増えています。中国語でゴルフに関する話題等で交流することができれば、プレーはより楽しくなりますし、ビジネスにもつながるかもしれません。
A:好球!王总,您打得好远。有什么秘诀吗?
Hǎo qiú! Wáng Zǒng, nín dǎ de hǎo yuǎn. Yǒu shénme mìjué ma?
ナイスショット!王社長、よく飛びますね。何か秘訣はありますか?
B: “死不抬头,绝不用力”。一定要记住这八个字。
”Sǐ bù tái tóu, jué bù yòng lì”. Yídìng yào jìzhù zhè bā ge zì.
「決して頭を上げず、力まないこと。」この八文字を忘れないことですね。
A:噢,原来如此!我打球时总是习惯把头抬起来。看来,今天我的总杆数要降到一百以下了。
Ō, yuánlái rúcǐ! Wǒ dǎ qiú shí zǒngshì xíguàn bǎ tóu tái qilai. Kànlái, jīntiān wǒ de zǒng gān shù yào jiàngdào yì bǎi yǐxià le.
おお、なるほど!私は打つときに頭が上ってしまいます。これで今日のスコアは100をきれそうです。
中国のゴルフ場では、ラウンド終了後、キャディーからチップ「小费(xiǎofèi)」を要求されることが多々あります。これは、チップがキャディーの主な収入源となっており、当然の報酬と考えられているためです。「図々しい!」と憤慨してチップの支払いを拒絶すると、キャディーにとってはタダ働き同然となるので、トラブルに発展する可能性もあります。チップは厳密には支払う義務はありませんが、「郷に入っては郷に従え」ですので、支払う用意はしておく方がスマートです。
中国での働き方改革は実現するか?
2017/07/28
Category :
最近は中国の日系企業の人事制度以外にも日本国内の企業の人事制度も数社、手掛けたりしています。私が人事制度のコンサルティングを始めたのが1991年でしたから、制度ばかりやってはや25、6年が経ちました。そのうち初めの10年は日本の代表的な人事制度である職能資格制度、その後の15年くらいは中国の職務給制度と、2つの大きな制度を経験してきたことになります。まあ、私がこの仕事を始めた翌年(1992年)にバブル景気が破たんしましたので、私自身がバブル景気を謳歌できたのはわずか1年足らず、と言いますか、栄枯盛衰と言いますか、確かにつらい時期を経てきたわけではありました。
今担当している日本の企業のひとつでは、複線型のコース選択制の構築・導入を進めています。一般職、地域限定職、総合職、専門職、管理職の5つのコースから、社員の希望や適性に応じてキャリアパスを選ぶことができるというものです。従来までは単一のコースしかなかったため、ポスト不足や昇給との兼ね合いから無理やりポストを作ってしまった結果、役職者が全体の25%まで膨れてしまい(企業の管理職比率は平均で11%)、マネジメントラインが機能しなくなってしまっていましたが、これで社員の進級先が広がりましたので、徐々にきれいなピラミッドを形成する組織に変わっていくことかと思います。
日本では最近、盛んに働き方改革が叫ばれており、必ずしも毎朝会社に出社しなくても、いろいろな働き方があってもいいんじゃないの?という風潮が高まりつつあり、この複線型コースも大きく言えば働き方のひとつになるわけですが、今まで中国で総合職だとか一般職だとかの区分で人事制度、キャリア制度を作ったことはありませんし、おそらくまだそこまでの選択の余地が用意されていないのかとも思います。せいぜいあっても管理職と専門職程度です。ましてや地域を限定して勤務するという選択は、もともと中国人社員は転勤や異動を嫌がる傾向が強いのと、会社側に立って考えてみても、転勤を伴う人事異動が整っていない、そもそも転勤させるほどの受け皿(分公司やグループ会社)がない、という背景から、言ってみれば社員全員が地域限定のようなものでもあります。
ただ、働き方の選択という意味では、おそらく中国人は日本人以上に割り切って、また合理的に考えると思うので、今後は在宅勤務だとかサテライトオフィスだとかが急速に整備されていくような気がします。それだけでも北京や上海、広州の通勤渋滞が緩和されるのはよいことです。経済学的には国民の所得が増え、余暇の選択肢が広がったり、それに伴う消費が伸びていくに従い、国民の金銭に対する欲求の比重は徐々に下がっていくみたいですので。
2017 給与情報・福利厚生分析レポート_Vol.7
2017/07/21
Category :
前回は福利厚生制度の構築や直近のトレンドについて取り上げた。今回は、中国籍人材の世代別の特徴やキャリア意識の傾向、日系企業の採用トレンドを紹介する。
70后 80后 90后世代の特徴
中国では、生まれた世代別に人々を70后、80后、90后とよく表現する。「后」は「後」を意味しており、70后は1970年代生まれ、80后は1980年代生まれ、90后は1990年代生まれを指している。現在の就業者における各世代の割合は70后(47歳以下~)、80后(37歳以下~)が大部分を占めていることもあり、若手人材である90后(27歳以下~)の採用ニーズが高まりつつある状態である。
70后は、時代背景として文化大革命時代に幼少期を過ごし、中国教育部が定めた“211工程”や“985工程”と呼ばれる、重点投資大学のレベル向上・発展への取り組みを加速させた時代に身を置いている。よって、勤勉で責任感が強く、上昇志向が高い人材が多く存在すると言われている。
80后は、改革開放政策による一人っ子政策の真っ只中を生き、“小皇帝”や“小公主”と呼ばれる程、厚遇を受けて成長してきた人が多いとされる。特に都市部ではインターネットや携帯電話等の情報網が普及したことで、海外文化も柔軟に吸収し、個性や個人の生き方を大事にする人材が多いと言われる。
90后は、市場経済の発展と更なる情報網の広がりにより、高所得世帯が増加して海外留学を経験することが当たり前の環境で成長してきたため、80后よりもさらに特殊世代と揶揄されることも多い。
実際に日本語学科を卒業した中国籍人材の多くは、いわゆる英語人材と比べると安定志向で内向的な傾向があるといわれ、こうした傾向が仕事面に表れることもある。また、90后は仕事よりプライベートを重視する傾向が強く、80后は仕事とプライベートのメリハリを求めて、残業や非生産的な業務への関心が薄いことが多い。70后は、長時間労働も厭わず仕事に没頭する傾向があるといわれている。
人事部や経営層の抱える人材の悩み
中国における人材活用の課題として、多くの企業が「短期離職」と「生産性の低下」を挙げている。具体的には、中間管理層の社外流出や、抜擢人材のパフォーマンスが期待値よりも低い、また配置の不適性による効率低下等の問題である。そもそも中国では、日本の正社員のような働き方はなく、有期雇用契約(1年~3年等)を更新して働くことが一般的である。若手世代であれば、ある程度の経験を積んだら自身のステップアップのために次の職場へ移っていくことが多く、中堅世代になるとより高いポジションや年収を求める傾向が強くなる。人材の能力と経験で給与が決まる中国では、自社の発展はもとより、個人の成長につながるキャリアステップが踏めるかどうかが解決の糸口に繋がるはずである。
以前の記事でも研修について触れたが、日系企業が得意とする従業員への教育研修の取り組み、特に誰もが通過点として受けてきたOJT(On-the-JOB Training)は、上記の人材活用の課題を解決するための施策として、中国でも生かせないだろうか。また、人事考課という大枠から脱却し、態度考課や能力考課で個々人の管理を行っていくことも求められてくるだろう。
時代に合わせた仕組みづくりを
現在、中国籍大学生の人気就職ランキングでは、中国系企業や欧米系企業でトップ30位までを占めており、日系企業は40位代以降にランクインしている状況である。地理的には中国と日本は近いものの、働く価値観や給与制度については中国企業と欧米企業との共通項が多く、依然中国人にとって欧米企業の方が馴染みやすいといえる。在中国日系企業は、自社が望む優秀な人材を採用していくためにも、人事制度の変更や処遇変更を視野に入れて対応していかなければいけない過渡期に入ってきているのではないだろうか。
(以上)
毎年パソナが実施する給与情報・福利厚生分析レポートは、下記よりご参照くださいませ。