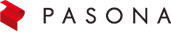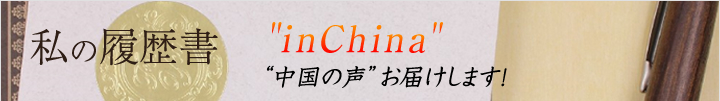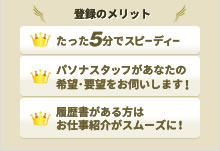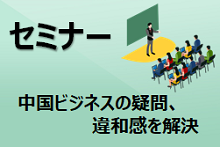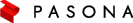中国就職に興味はあるけど、具体的なイメージがつかめない。将来のキャリアがどうなるのか不安だ。生活で困ることはないだろうか。みなさんはそんな疑問や悩みを抱えていませんか? “私の履歴書 inChina” では、そんなあなたに今まさに中国で働いている人々の“生の声”をお届けします! このコラムに登場する様々な人々のリアルな中国物語を通してぜひ“中国で働く将来の自分”を見出してください。
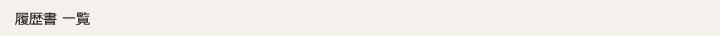

2015/09/07
上海 財務コンサルティング会社 中野さん
中野さんは、2014年の2月から上海にある中国系の財務コンサルティング会社で働いていらっしゃいます。本日は、中野さんのこれまでの中国との関わりや中国語への思いについてお伺いしたいと思います。
-これまでの経歴についてお聞かせください。-
大学卒業後、日本の不動産会社にて約2年間勤務いたしました。その後、オーストラリアでワーキングホリデーを行い、また台湾で半年ほど語学留学をしました。帰国後は、日本にて中国系メーカーの通訳翻訳業務を経て、2014年2月より現職の会社にて通訳翻訳業務担当として勤務しています。
-中野さんと中国の出会いについてお聞かせください-
高校2年の時に修学旅行で北京と上海に行ったのが私にとっての初めての中国でした。正直、それまでは中国に対してはいやなイメージがあったのですが、実際に行ってみて見方が大きく変わりました。北京で天安門などの歴史的建築物に触れて中国という国の魅力を感じ、また、上海では中国の人に親切にしていただく経験をして中国人が好きになりました。何があったかと言うと、上海で私が修学旅行のお土産としてチャイナドレスが欲しいと言ったんですね。そしたら、なかなか見つからない中、同行していた中国人が一緒になってすごく歩いて探してくれたんです。私だったらそんなリクエスト急に言われたら「チャイナドレスなんかない…。」と思うのになと(笑)。一緒にいた中国人は「気にしないで、あなたたちと歩いているのが楽しいから。」と言って一生懸命探してくれました。その出来事がとても印象的だったんです。また、中国の人はお給料が低くてもお客さんだったらご馳走してくれますよね。そんな経験を通して中国人は優しいなと感じました。
-高校の修学旅行をきっかけに中国に関心をお持ちになったとのことですが、その後の進路はどうされたのですか?-
中国での大学進学も考えたのですが、将来の就職のことも考え、また日本できちんと日本語で中国語を学ぼうと決めて、日本で中国に留学できる大学に進学することを決めました。大学2年の時に、南京師範大学の語言中心に留学し、語学と日本経済の科目を履修しました。留学先が南京だったので、留学を決めた当初は周りから「南京なんかに行って大丈夫?」と心配されたりもしましたが、南京では皆さんとても優しく、良い人ばかりでした。
就職活動はもちろん日本でしたのですが、中国語を仕事にしたくないと感じていました。中国語が好きすぎたので、趣味に止めておきたかったからです。好きな中国語を仕事にすることで無理に勉強したりしたくないと思いました。そのため、卒業後は中国語と関係のない不動産会社に勤務しました。数年の勤務後、英語も習いたいと思い、ワーキングホリデーを利用してオーストラリアのシドニーとブリスベンに滞在しました。日本料理屋とファームで1年程働いたのですが、オーストラリアに来て、やはり自分は中国語が好きで、中国語をしっかりやりたいと気づき、一度日本に帰国し資金を貯めた後、今度は台湾に渡りました。
-再び中国語の世界に戻ってきたのですね。(笑)台湾では何をされていたのですか?-
台湾では、4か月間語学学校に通っていました。中国語は英語と違って漢字がイメージできれば日本人なのでやはり意味が想像できるんですよね。中国語は単語やことわざなんかも面白いですしね。中国語でペンのキャップは「笔帽」と言うのですが、これは「筆の帽子」という意味で、そんなところにも表現がかわいいと感じたりします。
語学の勉強は楽しかったのですが、台湾での就職は考えませんでした。台湾には日本語の上手な台湾人がたくさんいますし、当時は、給与水準もそれほど高くありませんでした。何よりも、台湾に着いた時に「あまり日本と変わらないな。」と思ったんです。これは困らないなと思った。自分としては、困らないと成長がないと思う。困るから、考えて、考えるから、成長がある。結局、語学研修を終えてまた日本に戻ることにしました。
日本に帰ってからは、中国系メーカーのアフターサービス部で通訳翻訳の仕事をしました。日本の品質管理の担当者が書いたレポートの中国語訳や中国人上司と日本人上司の間に立って簡単な通訳をしたりしていました。その会社では1年半くらい勤務していましたが、その過程で自分の中国語レベルでも、そこそこ働いていけると自信がつきました。そして、より中国語を上手になりたいと考えた時に、日本で中国語に関わる仕事をするよりも中国に行って働いた方が良いと判断しました。また、これまで中国や、台湾、オーストラリアなど海外で生活した経験はありましたが、実際に働いてみた経験はなかったので、結婚したらもう海外で働くチャンスもないだろうなと思い、中国での就職を決意しました。